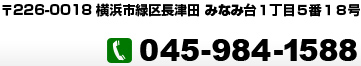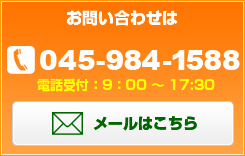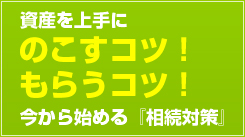農家、農業のあり方についてその11 [農業について考える]
相続税についての農地の納税猶予制度はよく、入口は比較的甘く、出口が厳しいと言われます。
確かに納税猶予申請時は、これから営農する意思をしっかり持っていればあとは書類を整えるだけですが、出口すなわち20年後または申請人が亡くなるまでという、の遠くなるような期間農業を継続していることが絶対要件ですから、その苦労は並大抵のものではありません。
人間は誰でも年老いてきて体もキツくなるし、病気になることもあるでしょう。また農業相続人を中心として一家で手伝うといっても、少子化で手伝い手で減ってくるし、第一跡継ぎが農業を継がないケ?スも出てきたら、老夫婦がいつまで経っても農業をやめられないことになってしまいます。
また市民菜園など他の人に貸していたら納税猶予は受けられません。とにかく自分と自分の一家で、農地を20年間または農業相続人が死ぬまで維持継続しなければならないのです。
農地を生産の場としている農家なのですから、農家を一生やりつづけての農業投資価格としての課税だ、と言えばそれは正論ですが、この少子そして何より高齢化が急速に進行している我が国の実態を考えれば、きつすぎるハードルではないでしょうか。
またこういう見方もできます。それは農地の生産性の側面からです。
現在の納税猶予制度の下では、あくまで自分の農地は自分で守れという方針ですから、結果的に70歳、80歳の方が体にムチを打って働くことになりますが、こうしたお年寄りがいくら働いたところで、その農地からどれだけの農作物が生産されるでしょうか。
自分たちが食べていき、そして親戚や近所におすそ分けをする程度の生産量しか上がらないとすれば、そうしてまで維持する農地は国にとって有益な農地と言えるでしょうか。
″たわけ者″という言葉があります。これは文字どおり田を分けるつまり分割することほど愚かな行為はない、という意味です。それほどまでに農耕民族である我々日本人は田畑を守り通そうとしたのです。
ところが明治維新後急激に近代化され、就労人口も第一次産業である農林水産業から製造業を中心とした第二次産業そしてサ?ビス業、金融業、運輸業などの第三次産業へと大幅にシフトされてきた現代日本では、そうした土地に対する執着も薄れてくるのはある意味致し方ないことですが、農家にあってはその生産拠点である農地、もっと言えば土地全体に対する執着心は並大抵のものではありません。
というのも私がかねてから申し上げているように、ご先祖様からの遺伝子がそうさせているのです。
強欲でも何でもなく、土地を生産の場としてきたからこそ、土地を失うことは極端にいえば〃家〃を失うことなのです。
ですから核家族社会が主流で、過去のご先祖様の生き方をよく知らない今のサラリ?マン諸氏が、余った土地は売れば良い、という感覚と、根っから土地に執着している農家の方とは全く土地に関する考え方が相容れないのです。
私はどちらが正しいなどということを全く言うつもりはありません。
私が言いたいのは、農業を営む方はそれほど土地を大事に思う考え方が、体中にこびりついている、そしてそれは先代から脈々と受け継がれてきている考え方であるということです。
この事実を農業をやっていらっしゃらない方にも知って頂きたいということです。