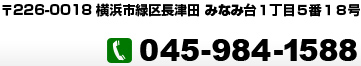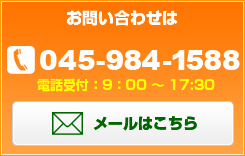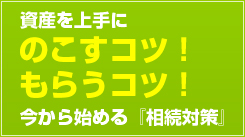セカンドオピニオンについて考える その17 [セカンドオピニオンにについて考える]
事実、大手の税理士事務所、税理士法人は、相続税の申告に自信のない税理士に、
評価を外注させて下さいとか、資産税にこれから本格的に取り組もうとしている税理士
向けに資産税セミナ?を企画したり、DVD、CDを販売したりする動きが活発になって
います。
益々税法が複雑化、専門化する時代にあって、間口を広げようとする動きよりも、
専門性を追及する動きが、これから都内を中心に徐々に地方にも広がっていくでしょう。
その時に地方で登録し、活躍されている税理士さん方は、町医者でやっていくべきか、
それとも専門性を追及する方向へ方向転換するか、いずれ選択を迫られているでしょう。
私小池税理士事務所は、地域柄町医者を標榜しますが、徐々に資産税にウェイトを
置いていくことになりそうです。
資産税は相続税だけでなく、所得税、法人税などの複数税目がクロスする難易度の
高い分野です。その他民法、不動産業法等周辺知識も併せて要求されます。
これだけで本当に奥の深い分野です。
自分も気が付いてみれば56歳、この税理士業界に足を踏み入れて30年以上経ち、
あと元気でどの位の期間活動できるか分かりませんが、とうに折り返し地点を過ぎて
いることだけは確かです。
残りの税理士人生は、資産税にもっと傾注したいという思いは段々強くなっています。
ただ節度は持って仕事はしたい。人のやっている仕事のあら探しをするようなやり方
はしたくありません。
本当に良い意味で税務、会計の世界において、「セカンドオピニオン制度」が定着し、
お客様に役立つ制度になって欲しいと願っています。
そのためには、税理士一人一人が自分の持ち場、専門分野をもっと明確にすると
同時に、税理士同士の良好な関係での提携、連携が必要でしょう。
今は過渡期ですが、税理士業界発展のためにも、税理士が個人事業主の感覚から
洒脱し、お客様、相談者から見てどういう存在になることが求められているのか、考え
て欲しい、勿論自分も含めて。
そして税理士会としても、税理士の水平的構造を改め、垂直的、階層的構造化が進む
よう制度設計をして頂きたいと思います。
以上一通り総論をまとめたところで、17回に亘るテ?マは完結します。