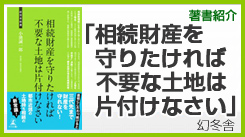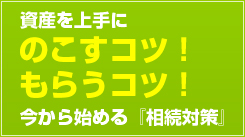勤務税理士時代を回顧する その7 [勤務税理士時代の回顧]
自分の無力さを十二分に思い知ったそれから2年間は、自分でいうのも何ですが、T先輩に反抗することなく、ひたすら実務処理能力を少しでも上げるべく、謙虚な気持ちで仕事に向かうことができました。
また受験の方も順調に推移し、昭和56年の税理士試験で、無事「財務諸表論」に合格し、次の年には自分が苦手としていた「簿記論」にも合格し、仕事、勉強ともに充実した2年間でした。
そしてI先生のおっしゃっていた会計事務所に入って丸3年が経ちました。
I先生は特別な事は言われませんでしたが、入所して3年間経ってから私をT先輩の補助者から外し、担当者に格上げして下さいました。
やったあ。やっとこれで私もI税理士事務所の職員として正式に認められた、と大変嬉しい、と同時にほっとした気持ちになりました。
担当者として担当をした顧問先は、自分がT先輩の補助者として仕事をしてきた顧問先ばかりでしたので、特段変わったことはありませんでした。
ただ、これからはT先輩に一つ一つ相談し、頼っていくことは基本的には出来ず、自分の力で解決していかなければなりませんから、いくらやっている仕事の内容に変化はないとはいえ、責任が重くなったことに対して、身の引き締まる思いであったことは言うまでもありません。
受験の方は、税理士試験の一番の本丸である「法人税法」にとりかかっていました。
この「法人税法」は、「財務諸表論」と並んで、私の好きな受験科目の一つでした。
「財務諸表論」は、会計原則の理論を勉強する学問ですから、会計の考え方、捉え方を学ぶには最高の科目でした。
「法人税法」は、後で分かったのですが、「所得税法」、「相続税法」などと比べて、法令、通達が整備されていて、法体系がきわめて精緻ですっきりしています。
一例を挙げれば、「法人税法」は会社にとっての収益、費用はすべて「益金」「損金」として処理します。
それに対して、「所得税法」では、所得の種類を10種類に分け、それぞれの所得について課税対象となる所得がまちまちです。つまり収益?必要経費=所得になるのですが、その所得の2分の1が課税所得になったり、必要経費の方が収益より多くても、つまり赤字の場合でも、その赤字を切り捨ててしまうとか、収益?必要経費からさらに50万円を控除するとか、所得の種類によって課税対象となる所得が違うのです。
これはそれぞれの所得の性質、担税力に応じて差異を設けている、とのことですが、だとすれば一時所得という最も担税力の高い所得に対して、所得を計算する上で50万円を控除した上で2分の1を課税対象としているのは何故でしょうか。
もともと一時所得は悪く言えば、あぶく銭的な所得ですから、そうした優遇を設けるのは到底納得のいくものではありません。
その点、法人税法は収益=益金、費用=損金という非常に分かりやすい構造になっています。個人と違って会社は元々営利を目的として作られていますから、収益の種類によって課税に差を設ける必要がない、どんな収益でも収益には違いがないからすべて等しく取り扱う、というのが「法人税法」の考えです。
また「法人税法」の課税対象所得の計算は、「誘導法」と言って、企業会計原則に基づいて作成された「財務諸表」をベースにして、会計上の収益、費用と、法人税法上の益金、損金との差異を別表4において調整する、というスタイルを採っていますので、基本的には、会計上の収益=法人税法上の益金、会計上の費用=法人税法上の損金に一致するのです。
ですから、財務諸表論で学んだ考え方が、殆ど法人税法上にも適用されるので、財務諸表論をしっかり学んだ受験生にとっては、大変に取り組みやすい試験科目でした。、