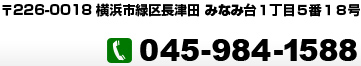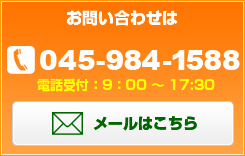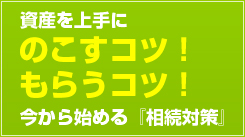農家、農業のあり方について その5 [農業について考える]
大人が自由にいつまでも浮かれて物質文明を貪っている。それを見ている子供たちも大人のマネをする。その子供たちが大人になり子供を産み、その子たちにも同じように伝播していく。
自由には限度がある、腹八分という考え方は、生活をエンジョイしている時にはほとんど頭になかったのです。
そして挙句の果てに、お金があれば世界中から欲しい物が何でも入ると慢心した日本人は、エコノミックアニマルと皮肉られるようになってしまったのです。
そして最近はアキバ系、萌系などという遊びとはいえ、恋愛気分までお金で買う時代になってしまったのです。
生活が楽になり自由になるのはよいことなのですが、私たち日本人は忍耐、我慢、辛抱することそして束縛されることを極端に厭うようになりました。
その結果が就職状況にも顕著に現れ、農林漁業の第一次産業に就く人の割合は先進国中極端に低く、製造業を中心とするモノ作りである第二次産業も3K業種として敬遠され、サービス業を中心とする第三次産業にどんどんシフトしているのです。
いかに楽をしてお金を稼げるかという観点から職業を選択しているのですが、サービス業の世界もそんなに甘くはありません。人とのコミュニケ?ション能力を多く要求されるサービス業は、束縛を嫌い、人との接触特に争い、口論といったお互いの考え、個性が全面的にぶつかりあう局面を極力避けてきた自由世代は、仕事とはいえお客様に上司に合わせるのが苦手で、それが大きなストレスになってきました。
行きすぎた自由が招いた弊害、それは人間を個人個人に分断し銘々勝手な行動をとる結果、集団としてまとまらなくなってしまう、そして個々に分断された個々人は、集団、組織との付き合い方、関わり合い方をろくろく知らず、ますます個人の殻に閉じこもるようになってしまうことです。
自由という言葉は何とも響きのよい言葉ですが、自由を放任してしまうと、人間の忍耐力、想像力を奪い取って、人間としての社会性を失わせてしまう恐ろしい結果となります。